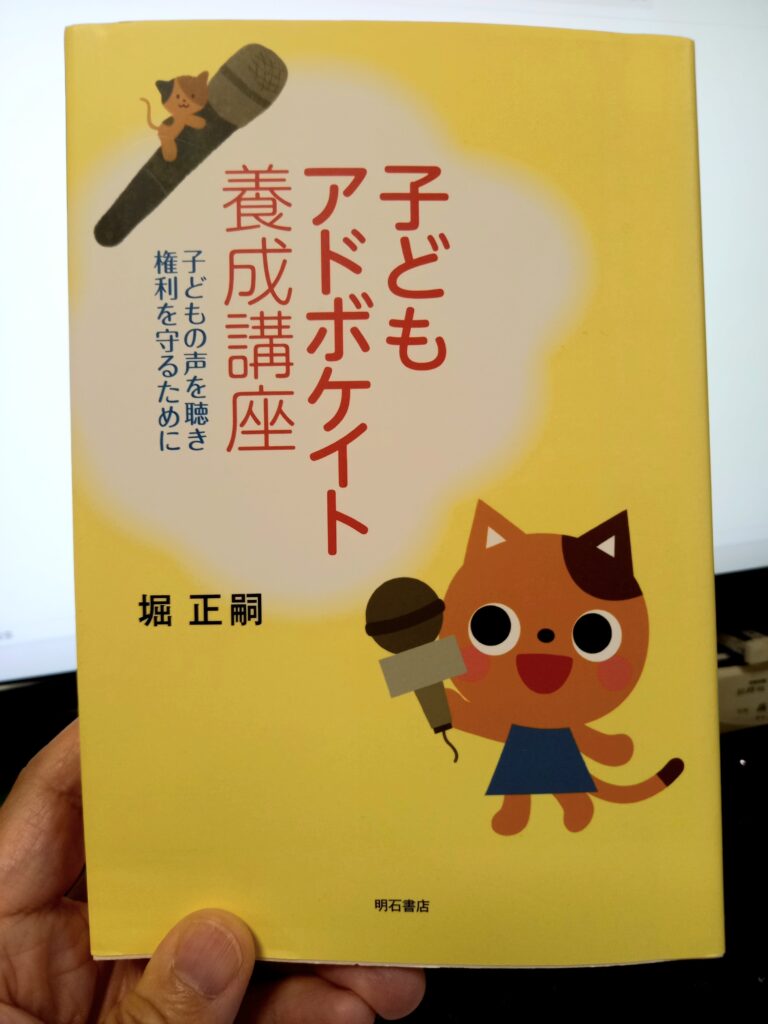2025.05.16
子どもアドボケイト養成講座を受講して
本講座受講のきっかけは、北区でも児童相談所と一時保護所の開設準備が進んでおり、その運営において、相談や入所にいたる子ども1人1人の思いや考えが十分に尊重されるために、アドボケイトの役割が重要との指摘を受け、自分も理解を深めたいと考えたからです。
受講してその役割の重要性を学ぶことができました。例えば、保護者からの虐待で傷ついている子どもにとって、自己の存在は暴力により貶められている状況であり、不安や恐怖、大人への不信を感じ、自己肯定感や意欲を奪われている中、安心して自分の気持ちを表し、言葉で意見を述べることも容易いことではありません。
そんな時に、アドボケイトは、子どもが保護者と離れ、今、どんな思いでいるのか。どんな状況を望んでいるか。誰とどこで、どう暮らしていきたいかなど、声なき声、声にならない声を聴きとり、小さくされている声を、大きな声にして表し、子ども自身の処遇について子どもの意見が反映され、自らの人生の主体者、主権者として選び取っていけるように、子どもとともに取り組む子どもの人権の専門家だと学びました。
また、子どもは本来、力のある存在ではあるが、大人との社会的な力の差があるという点では、社会的擁護が必要な子どもだけでなく、全ての子どもが自由に声をあげ、行動でき、子どもの最善の利益が優先して考慮される必要があります。
そのために、家族・保護者をはじめ、保育園、幼稚園、子ども施設、学校、民間施設など、子どもに接する大人、スタッフの知識・スキルとして、子どもアドボケイトついて学ぶことができる。また子どもアドボケイトの配置をしくみとして導入する等、子どもの生活の場においても、子どもアドボカシーが行なわれることが、子どもの人権尊重や豊かな社会につながるのではと感じました。
現在、北区でも子どもの意見を様々な行政施策に反映していく仕組みとして、施策を準備していく過程で子どもの意見を直接聞く、子どもにアンケートを取る、子どもの権利委員会に当事者である子ども自身の参加を保障するなどにも取り組んでいます。
例えば、学校の運営においても、子どもがどんな声や願いを持っているか、子どもの声を表す、子どもアドボケイトを位置づけることも重要ではないかとの問題意識を持ちました。
また、自分も少なからず、子ども自身から相談を受ける場合があります。
その際には、講座で学んだ、①表出する支援、②形成する支援、③表明する支援、④実現する支援ということを常に意識し、目の前にいる子どもと自分は別の人格、違う存在だということを自覚し、自分の子どもに対する姿勢に偏見はないか、良かれと思いこどもを支配していないか、常に謙虚に問いかけながら、子どもの自己決定を大切にする立場で行動していきたいと考えました。
最後に、子どもアドボカシー、子どもアドボケイトの取り組みの充実は、人権尊重と民主主義が拡がる大きな力との学びを得ることができました。