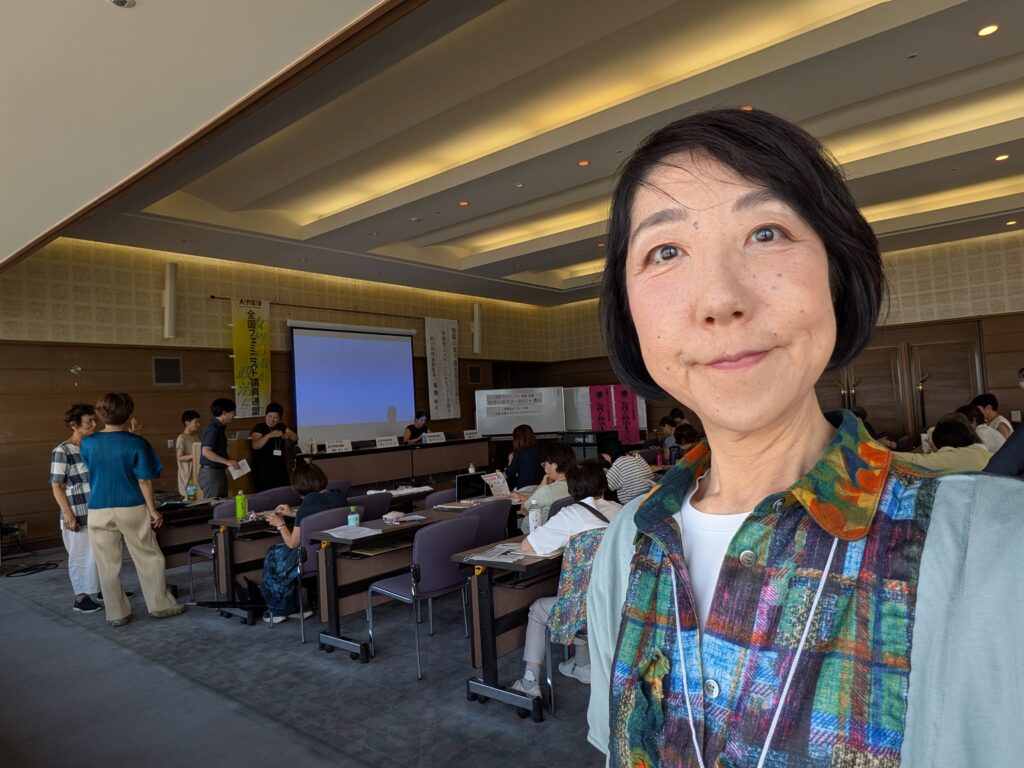2025.08.07
情報の海で迷わないために~多様性とメディアリテラシーの接点~
8月7日(金)~8日(土)、サマーセミナーが、香川県高松市レグザムホールにて開催されました。
7日(金)の基調講演では、かつて森喜朗首相の番記者を担当した、朝日新聞編集委員の高橋純子さんがお話しました。(以下要旨)
冒頭、小選挙区中心の選挙制度の課題について、勝者総どり制度だと指摘。1票でも多くとった候補が当選し、他候補への票はすべて死に票となって捨てられる。ほとんどは最大政党が当選となる。この勝てば官軍といえる政治状況を最大限に利用したのが安倍政権。
官邸で出た案をろくに議論もしないで決める、強行採決が当たり前にまかり通る事態を招いてきた。異論を出し合い、議論をつくし、合意形成をしながら政策や法案を作り上げていくという当たり前の国会運営がなくなってしまった。閣議決定がはびこった結果、国会での民主主義のプロセスが主権者に見えなくなったと指摘。
また、安倍政権は対立をあおる政治手法をとった。その結果、敵か味方かに決めつけ、対話によって歩み寄ることをしない、分断政治が生み出されていった。それが先の参院選での右派ポピュリズムー大衆迎合主義―を生んだのではないか、と問題提起。
そして、右派ポピュリズムの台頭を、『ポピュリズムの仕掛け人』政治評論家で作家のジュリアーノ・ダ・エンポリの著作の一節を紹介。ポピュリズムは「大衆対エリート」の構図を作りあげ政治をカーニバル化することにより、大衆の熱気を生み出すーと。この流れは、7月の参議院選挙にも通じるものではないか。
今、SNSの影響が大きく、新たに登場した政治家たちは、選挙で支持を集めるためにSNSを使って分断を進めている。公人の記者会見と政党の広報活動を混同している政党まで現れている。記者会見も開かずSNSで報告しますと。説明責任も果たさず問われずにいることができる。これは私達メディアの非力でもある。
SNS、ワンクリックで自己愛に陥る時代は、すぐ結論が出ない政治、消費者をいらだたせる。メディアや議会の仲介機能は危うくなり、他者への想像が及ばなくなってきていると指摘。
最後に、哲学者の古田徹也さんが語ったという「ありきたりの言葉ではない、常套句ではない表現を選ぶことが大切」という言葉や、映画監督の是枝さんにインタビューした際、「熱狂の渦の中にある時、まず引いてみることが大切」「日本人は、『この先』をやたら聞きたがるが、答えを安易に求めがちな傾向はマッチョなリーダーについていけば安心という構図につながる。」とのお話も紹介し、
政治のリーダーは私たちが作る、つまり私たち自身が自分を主人公にすること、そのためには、いい文化、いい音楽、いい文学、いい映画を見て、自分の個性や感受性を磨き、他者への想像力を養っていくことが大切ではないかと訴えました。